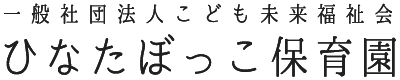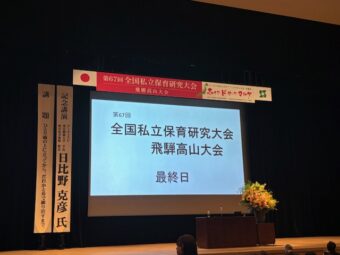第67回全国私立保育研究大会~飛騨高山大会~
6月11日から13日に開催された、
第67回全国私立保育研究大会「飛騨高山大会」に、
今大会のテーマは
「“ニッポンのまんなかで“こどもまんなか”を語る ホイク・ド・ターケ・マルケ」
ホイク・ド・ターケ・マルケとは、
「ドターケ」→「一般的に、ある分野に溢れんばかりの情熱を傾けている人」
のことを、敬意を込めて呼ぶ「○○バカ」の岐阜言葉。
「マルケ」→「ひとが沢山いる様子」。
保育研究大会に受け継がれている雰囲気を
岐阜流に表現した言葉だそうです。
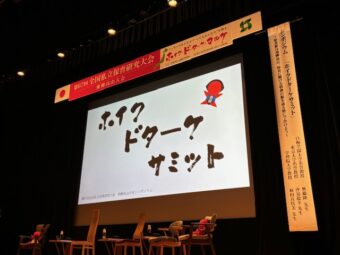
1日目は、
高山市民文化会館にて約1800人の保育関係者が集まる中、
開会式、表彰式、行政説明、シンポジウムが行われました。
シンポジウムは、長年保育や幼児教育の研究をされてきた
白梅学園大学名誉教授の無藤隆先生、
東京大学名誉教授の汐見稔幸先生、
学習院大学文学部教授の秋田喜代美先生を講師に迎え、
保育の世界に入ったきっかけや、
喫急で考えている課題、
研究者や保育者へのメッセージなど、
テーマごとにお話ししていただくというものでした。
2日目は、
それぞれ24のテーマに分かれた分科会に参加しました。
参加した分科のテーマは、
第8分科会『小学校との連携と接続を考える』
第9分科会『チームを育む保育ファシリテーション
~園内研修コーディネーターの実践事例から~』です。
第8分科会の「ひだホテルプラザ」の会場には60名程の参加者がいました。
内容は、全国の保育園(4園)による研究発表と
議題に対するグループ討議・意見の発表、
岐阜大学教授の今村光章先生による講義です。
グループ討議では、札幌・神戸・東京から来られた
保育者と意見を交換することが出来、
小学校との連携に対する取り組みにも
それぞれの地域による特色や課題があることを学ぶなど、
貴重な時間となりました。
3日目は、
東京藝術大学学長の日比野克彦先生を迎えた記念講演と
閉会式が行われました。
講題は『ひとり橋の上に立ってから、だれかと船で繰り出すまで』
日比野先生の幼い頃の体験が、
「アートで自身の考えを社会に発信していく!」と
表現の道に進むきっかけになったというお話が
とても興味深く、幼児期・児童期における体験の重要性を感じました。
また“作った作品に正解はない”とお話されていたように
表現した、そのこどもらしさに触れること、
表現を止めてしまうような声掛けをしないこと、
などを表現活動において大切にしていくことの大切さを改めて学びました。
3日間の研修を通して、
改めて“保育”の社会的役割を考える機会となりました。
保育士として目の前のこどもたちと向き合いながら、
どうしたら保育の質を高めていけるのか、考え、学び続けていきます。
中尾・赤岡